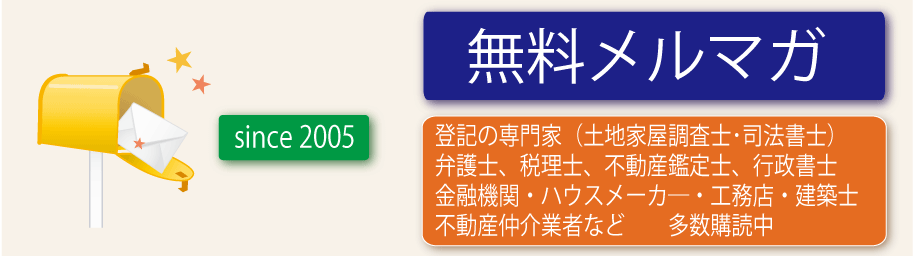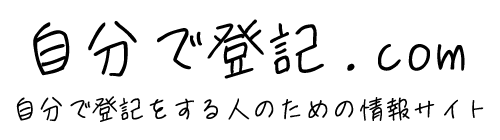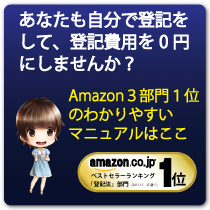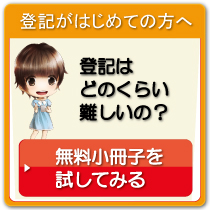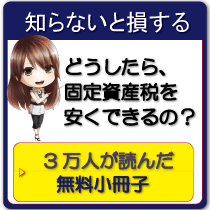新築したら、登記はしないといけないの?!
新築したら、登記はしないといけないの?!
自分で登記をする会です。
書籍『自分で登記をする会』ですが、おかげさまでAmazonベストセラーランキングの3部門で1位を取り続けることができました。
多くの方に購入していただき本当にありがとうございます。
購入していただいた方からのご感想です。
----- 購入理由 -----
専門家に依頼しない不動産登記申請の本は珍しいので、どのように説明がされているのか興味がありました。
----- 感想・ご意見 -----
物語形式なので作業の順番が分かり易く、とても楽しく読めました。
----- 購入理由 -----
建物表題登記を自分でやってみようと思っていたので。
----- 感想・ご意見 -----
大変参考になりました。まさに、知りたいことが書かれている、といった感じです。
---------------------------------------------------------------------
登記を物語で説明した登記のマニュアル
書籍「自分で登記をする会」好評発売中です。
登記のことが分りやすく書かれています。
自分で登記をしようと思ったら、まずはこの本から
---------------------------------------------------------------------
それでは、本題です。
今回も、お問合せをいただきましたので、情報をシェアさせて下さい。
疑問点やわからない箇所がありましたら、お気軽にお問合せ下さい。
今回のお問合せ内容です。
---------------------------------------
新築から一ヶ月以内に登記をしないと10万円以下の過料となると聞きました。
登記は、絶対にしないといけないのでしょうか?
---------------------------------------
答えは『No!』ですが、ケースによっては『Yes!』になってしまいます。
わかりにくい答えで申し訳ありません。
詳しく説明していきますね。
□ 過料について
1つだけ確実に言えることは、10万円以下の過料は、現状は気にしなくて大丈夫です。
土地家屋調査士のホームページに登記をしないと過料になると書かれたページがよくありますが、
あれは、依頼して欲しいので書いています。
自分で登記をする会では、情報を正しくお伝えすることに重きを置いています。
脱法行為はいけませんが、現状と裏事情をお伝えしていきたいと思います。
話の続きですが、
世の中には登記のされていない建物はかなり多いです。
おそらく世の中の1割以上の建物は登記がされていないように思います。
これら登記がされていない建物を『未登記建物』と言いますが、
未登記建物の所有者が過料になった話は聞いたことがありません。
登記研究会の中に、未登記建物を所有したり、実家が未登記建物の方がいますが、新築から60年以上経過していますが、過料にはなっていません。
過料とは、罰金や科料と異なり刑事罰ではなく行政罰なので、前科にもなりません。
この過料ですが、状況が変わり、過料が実際に適用される可能性はないとは言い切れませんが、まずそうなることはないと思われます。
何か変化がありましたら、メルマガにてお知らせ致しますね。
□過料となる登記とは
登記をしなくても、過料にはならないとわかったところで、
10万円以下の過料となると定められている登記は、どの登記であるか説明します。
不動産の登記には、大きく『表示(表題)に関する登記』と『権利に関する登記』の2つがあります。
『表示(表題)に関する登記』は、
・新築した際に行う、『建物表題登記(建物表示登記)』
・増築した、『建物表題変更登記』
・壊した、『建物滅失登記』
・一部を壊した、『建物表題変更登記』
など
物理的現況に変化があった際に行う登記です。
『権利に関する登記』は、
・ 売買し所有者が変わった 『所有権移転登記』
・ 不動産を担保にお金を借りた 『抵当権設定登記』
・ 新築し所有者であると第三者に対抗する 『所有権保存登記(保存登記)』
など
誰が所有者なのか、不動産を担保にしたお金の貸し借りなど
権利関係に変化があった際に行う登記です。
このうち、過料になるとされているのは、
『表示(表題)に関する登記』のみです。
『権利に関する登記』はしなくても過料となると定められていないのです。
なぜ、『表示(表題)に関する登記』だけが10万円以下の過料となるという法律があるのでしょうか。
固定資産税
固定資産税
固定資産税
そうです。固定資産税が絡んでくるからです。
例えば、
新築して、未登記の場合、
市区町村はその新築に気付かないことがあります。
そうなると課税できません。
市区町村は損をしますよね。
しかし、新築の際に登記をしてもらえれば、市区町村は新築したことに気付くので課税できます。
※現在では、建築確認申請から市区町村は情報を得ているようです。
増築も同じです。
新築に比べて市区町村は増築には気付きにくいです。
増築しても登記をしないと、市区町村は気付かない可能性があります。
そうなると、今まで以上に課税できません。
建物を壊した場合で登記をしないと、気付かれずに課税し続けられる可能性はあります。
これには、要注意です。
※マイホームとして使っている建物が取り壊された場合、建物には課税されなくなりますが、土地の固定資産税が上がるケースが多いです。
『表示(表題)に関する登記』は、建物がどうなったかわかり、固定資産税を課税する市区町村が欲しい情報です。
『権利に関する登記』は、売買で所有者が変わった場合は、法律で定めなくても必ず登記をしてもらえます。
相続して子供が所有者になったら課税する段階で所有者が気付きます。
相続した所有者は、市区町村に連絡して所有者の名前を変更するか、そのまま亡くなった人のままでも、納税してもらえれば市区町村にとっては損をすることはないですよね。
『権利に関する登記』の情報はどうしても欲しい情報ではないようです。
このような市区町村の事情から、『表示(表題)に関する登記』は10万円以下の過料となるという法律があるのです。
ただし、この仕組みは機能していないのが現状です。
ちなみに
『表題登記(表示登記)』の専門家は『土地家屋調査士』
『権利の登記』の専門家は『司法書士』
です。
終わりかと思ったでしょう(笑)
まだ、少しだけ続きます。
もう少しお付き合い下さい。
□ 不動産を担保にお金を借りると登記をしなければなりません
登記をしなくても、10万円以下の過料になることはなさそうですが、登記をしなければならないケースがあります。
それは、不動産を担保にお金を借りる時です。
不動産を担保にお金を借りる際は、必ず『抵当権設定登記』という登記をします。
この『抵当権設定登記』は、『未登記建物』にはできないのです。
新築の場合は、
『建物表題登記』
『所有権保存登記(保存登記)』
の後で、
『抵当権設定登記』をすることができます。
※抵当権設定登記は所有権保存登記と同時に申請が可能です。
不動産を担保にお金を借りようとすると、必ず登記をすることになります。
登記を拒否することもできますが、お金を貸してくれないでしょうね。
不動産を担保にお金を借りると、登記をしなければなりません。
逆に、未登記ということはお金を借りておらず、借金がないと言えます。
次回は、未登記建物についてのお話をしますね。
お楽しみに!
最新情報を確実に受け取れます!
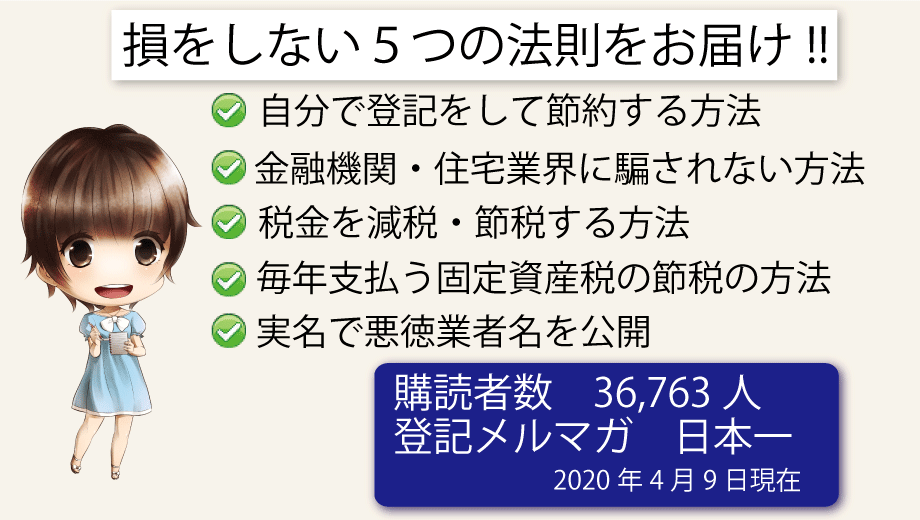
 麻美
麻美日本登記研究会は、あなたへ真実を伝えることを使命と考えています。
でも、ホームページに裏情報や実名などの情報を掲載すると日本登記研究会は営業妨害や名誉毀損などで損害賠償請求をされる可能性があるの。ホームページに掲載された情報は誰もが、いつでも読め、公開されているから。
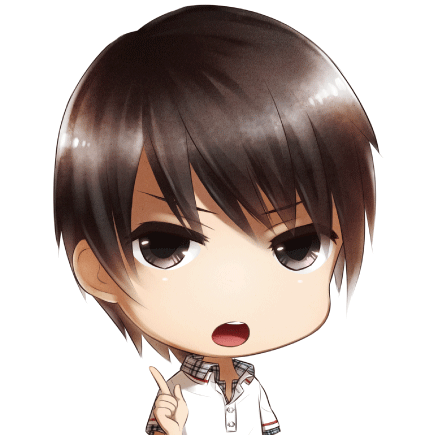 芳樹
芳樹そこで、ホームページに掲載しにくい情報は、日本登記研究会が発行する『メルマガ(メールマガジン)』にて個別に情報を届けています。
このメルマガの読者は3万人を超え、登記に関するメルマガでは日本一です。
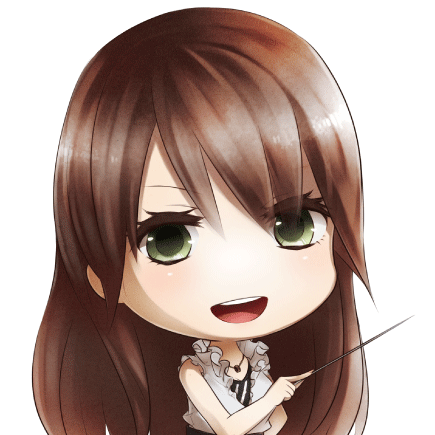 香苗
香苗なお、これまでに無料小冊子を受け取った場合は、既に読者登録されいますので、新たに登録する必要はありません。
 麻美
麻美無料の『メルマガ(メールマガジン)』を読まれますか?
下記の□の箇所に『あなたのメールアドレス』を入力し登録ボタンをクリックしてください。
これだけで登録完了です。登録完了後10分以内に、あなたへ『メルマガ(メールマガジン)』を送信します。
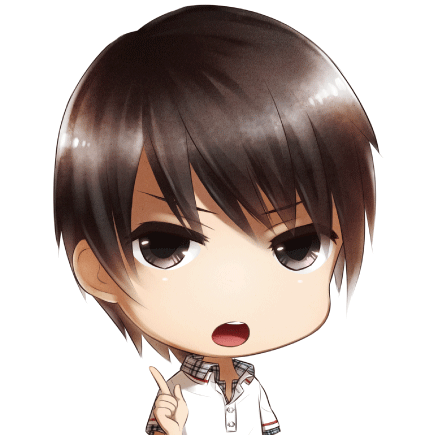 芳樹
芳樹『メルマガ(メールマガジン)』は不要になったら、簡単に登録を解除できます。
あなたにとって損なことは何もありませんよね。
今すぐ、真実の情報を受け取ってください。
裏情報・最新情報を無料で入手しましょう
メールアドレスを入力後、登録ボタンをクリック、次に送信ボタンをクリックで登録完了です。
解除される時は、解除ボタンを2回クリックするだけで簡単に解除できます。